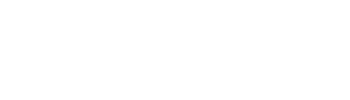履修方法等
1.学期
学年は、4月1日から3月31日までで、その学年は、次の学期に分かれています。
前学期 4月1日から9月30日まで
後学期 10月1日から3月31日まで
2.授業
- 授業時間割
授業時間割表は、毎月初旬に翌月分をClassroomで配信します。
授業時間割表の変更、休講、補講等がある場合は、その都度Classroomで配信しますので始業前等には必ず確認してください。 - 授業時間
1時限 2時限 3時限 4時限 5時限 9:00~10:30 10:45~12:15 13:15~14:45 15:00~16:30 16:45~18:15 - 集中授業
集中授業は、原則として夏季休業中及び冬季休業中に行われます。具体的な開講日・時限等は、授業時間割表にて確認してください。 - 休講
大学又は担当教員のやむを得ない理由により、休講することがあります。休講の場合は、その都度 Classroomで連絡します。休講の連絡がなく、始業時刻から15分を経過しても担当教員が教室に来ない場合は、事務室に連絡し指示を受けてください。 - 補講
休講した授業科目は、補講を行うことがあります。履修者は通常の授業と同様に受講してください。
3.履修方法
学則、教育課程表及び授業時間割表の定めるところに従い、各自が履修計画を検討し計画的に各科目を履修しなければなりません。
履修上の注意事項
- 必修科目、選択必修科目を含めて、卒業に必要な単位数以上を履修登録、修得してください。
- 同一時限に複数の授業科目を履修することはできません。
- 既に単位を修得した授業科目は、再び履修することはできません。
4.履修登録
学生は、各年度の各学期に履修する選択科目について、本学の定める期日までに学生ポータルから履修登録を行います。必修科目については、自動的に履修登録されます。履修登録がされていないと、授業に出席しても試験の受験資格が得られませんから、十分に注意してください。
履修登録完了後、任意に履修科目を変更することや、登録した履修科目を放棄することはできません。
履修登録の上限単位数(CAP制)
CAP制とは、授業科目の単位習得に必要な学修時間を確保する観点から、各学年において履修登録できる単位数の上限を定めた制度です。本学では、全学科・全専攻・全学年において1年間に履修登録できる単位数の上限を55単位としています。
5.授業の出・欠席の取扱い
- 原則として、授業開始前に出・欠席の確認を行います。
- 出・欠席の取扱いは次の各号によりますが、原則として、授業開始前に出・欠席の確認を行います。
- 出席は、本学の定めた出席すべき日時に本学授業に出席した場合をいいます。
- 欠席は、本学の定めた出席すべき日時に本学授業に出席しなかった場合をいいます。
- 欠課は、本学授業に出席した日のうちで、各授業時間において遅刻並びに早退に該当する範囲を超えた場合をいいます。
- 遅刻は、授業開始時刻、本学行事の日にあっては定められた登校時刻又は集合時刻の20分以内の遅れをいいます。
- 早退は、授業終了前、本学行事の日にあたっては定められた解散時刻前20分以内に退出した場合をいいます。
- 同一科目において遅刻、早退2回をもって1時限の欠課となります。
- 公認の取り扱いは、次の各号によりますが、公認願を事務室へ提出し学長が認めた場合に限ります。
- 授業中の負傷・病気に伴う治療の場合
- 忌引きによる場合(※休日等を含む)
父母(7日)兄弟姉妹(5日)祖父母(3日)伯叔父母(2日)
ただし、遠隔地に赴く場合は、必要最低限の日数を認めることができる。 - 伝染病発生並びに罹患による登校停止の場合
- 本人の責めによらない不可抗力の場合
原則として公認願は事前に提出するものとし、やむを得ず事後に提出する場合は、遅くとも3日以内(土・日・祝等含まず)に事務室へ提出しなければなりません。
6.選択科目の履修人数について
選択科目のうち、次に掲げる科目については、授業方法の形態及び教室の座席数の関係上、履修人数の制限を設けます。履修希望者が制限人数を超えた場合は、学内での抽選により履修者を決定します。
その他の選択科目についても教室の座席数等の事情により、人数調整の上履修者を決定します。
| 科目名 | 制限の人数 |
|---|---|
| 情報科学 | 40名 |
| 英語Ⅱ(日常英会話)A | 40名 |
| 英語Ⅱ(日常英会話)B | 60名 |
| 英語Ⅱ(日常英会話)C | 40名 |
| ドイツ語 | 40名 |
| 中国語 | 40名 |
7.臨地・臨床実習科目の履修に関する条件
実習科目を履修するためには、次表のとおりの履修条件を満たしている必要があります。
履修条件を満たしていない人は、履修できませんので注意してください。
看護学科実習科目の履修前提条件 <令和5年度入学生に適用>
| 区分 | 授業科目 | 時期 | 履修条件 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位修得済み科目 | 当年度履修登録済み科目 | |||||
| 専 門 教 育 科 目 |
専 門 科 目 |
健康生活を支える ための看護の原理 と基礎 |
基礎看護学実習Ⅰ | 1前 | 看護学概論 基礎看護技術Ⅰ |
|
| 基礎看護学実習Ⅱ | 2前 | 1年次の[専門基礎]全科目 看護学概論 基礎看護技術Ⅰ 基礎看護技術Ⅱ フィジカルアセスメントⅠ 基礎看護学実習Ⅰ |
基礎看護技術Ⅲ 基礎看護技術Ⅳ フィジカルアセスメントⅡ |
|||
| 健康生活を支える ためのライフサイクル別 看護活動 |
地域・環境実習Ⅰ | 1後 | 1年次前学期の[専門基礎]全科目 看護学概論 基礎看護技術Ⅰ 基礎看護学実習Ⅰ |
基礎看護技術Ⅱ フィジカルアセスメントⅠ 地域・在宅看護概論 高齢者看護学概論 |
||
| 地域・環境実習Ⅱ | 2後 | 【看護の原理と基礎】全科目 地域・在宅看護概論 地域・在宅看護活動論Ⅰ 地域・環境実習Ⅰ 高齢者看護学概論 高齢者看護活動論Ⅰ |
地域・在宅看護活動論Ⅱ 地域・在宅看護活動論Ⅲ 高齢者看護活動論Ⅱ |
|||
| 地域・在宅看護論実習 | 3前 | 【看護の原理と基礎】全科目 地域・在宅看護概論 地域・在宅看護活動論Ⅰ 地域・在宅看護活動論Ⅱ 地域・在宅看護活動論Ⅲ |
地域・在宅看護活動論Ⅳ | |||
| 成人看護学実習 | 3前 | 【看護の原理と基礎】全科目 成人看護学概論 成人看護活動論Ⅰ 成人看護活動論Ⅱ 成人看護活動論Ⅲ |
||||
| 成人・高齢者看護学実習Ⅰ | 2後 | 【看護の原理と基礎】全科目 成人看護学概論 成人看護活動論Ⅰ 成人看護活動論Ⅱ 高齢者看護学概論 高齢者看護活動論Ⅰ |
成人看護活動論Ⅲ 高齢者看護活動論Ⅱ |
|||
| 成人・高齢者看護学実習Ⅱ | 3前 | 【看護の原理と基礎】全科目 成人看護活動論Ⅲ 高齢者看護活動論Ⅱ 成人・高齢者看護学実習Ⅰ |
||||
| 小児看護学実習 | 2後 | 【看護の原理と基礎】全科目 小児看護学概論 小児看護活動論Ⅰ |
小児看護活動論Ⅱ | |||
| 母性看護学実習 | 2後 | 【看護の原理と基礎】全科目 母性看護学概論 母性看護活動論Ⅰ |
母性看護活動論Ⅱ | |||
| 精神看護学実習 | 3前 | 【看護の原理と基礎】全科目 精神看護学概論 精神看護活動論Ⅰ |
精神看護活動論Ⅱ | |||
| 看護の統合と実践 | 看護の統合実習 | 3後 | 【看護の原理と基礎】全科目 【ライフサイクル別看護】全科目 安全管理論 |
災害・国際看護論 総合判断育成演習 課題研究 |
||
※表中の【看護の原理と基礎】とは、「専門科目」の「健康生活を支えるための看護の原理と基礎」の科目を示す。
※表中の【ライフサイクル別看護】とは、「専門科目」の「健康生活を支えるためのライフサイクル別看護活動」の科目を示す。
*「健康生活を支えるためのライフサイクル別看護活動」の2年次後期にある実習については、2年次前期までの[専門基礎]科目すべてを単位履修済みであること。
*「看護の統合と実践」の3年次後期にある「看護の統合実習」については、3年次前期までの[専門基礎]科目すべてを単位履修済みであること。
リハビリテーション学科 理学療法専攻実習科目の履修前提条件 <令和4年度以降入学生に適用>
| 実習科目名 | 年次 | 履修条件科目(単位修得済み科目) |
|---|---|---|
| 臨床実習Ⅲ(総合前期) | 3 | 臨床実習Ⅱ(評価) |
| 臨床実習Ⅳ(総合後期) | 3 | 臨床実習Ⅲ(総合前期) |
リハビリテーション学科 作業療法専攻実習科目の履修前提条件 <令和2年度以降入学生に適用>
| 実習科目名 | 年次 | 履修条件科目(単位修得済み科目) |
|---|---|---|
| 臨床実習Ⅱ(評価) | 2 | 1年次、2年次必修科目すべて、かつ選択科目を含めて78単位以上 |
| 臨床実習Ⅲ(総合前期) | 3 | 臨床実習Ⅱ(評価)、作業療法総合セミナーⅠ(評価) |
| 臨床実習Ⅳ(総合後期) | 3 | 臨床実習Ⅲ(総合前期)、作業療法総合セミナーⅡ(評価と介入①) |
リハビリテーション学科 視機能療法専攻実習科目の履修前提条件
| 実習科目名 | 年次 | 履修条件科目(単位修得済み科目) |
|---|---|---|
| 臨地実習Ⅰ | 2 | 1年次、2年次前期までに修得すべき必要単位数(選択をを含めて)すべて |
| 臨地実習Ⅱ | 3 | 1年次、2年次までに修得すべき必要単位数(選択をを含めて)すべて |